原書は、Samuel P. Huntington : The Soldier and The State The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Belknap Press of Harvard university Press) 1956 である。
我が国における翻訳書としては、すでに市川良一『ハンチントン 軍人と国家 上/下』(原書房 2008年)が存在する。
我が国では全くの未知の概念・価値観である「ミリタリー・プロフェッショナリズム」の全容を理解するうえで、原書に当たる必要性を感じ、翻訳するに至った。非売品として2022年7月発刊。
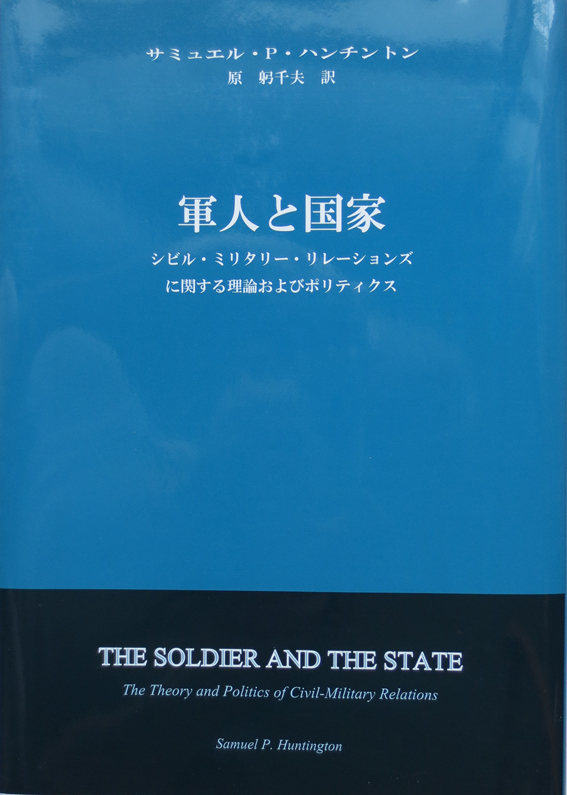
次に掲げる図書館に寄贈されている。
国会図書館
東大総合図書館
東大法学部図書館
京大図書館
京大法学部防大図書館
一橋大図書館
九大図書館
阪大総合図書館
防衛大総合情報図書館
慶応義塾大学図書館
早稲田大学図書館
目次
序文
序論 国家の安全保障とシビル・ミリタリー・リレーションズ 1
一.シビル・ミリタリー・リレーションズの形態を決める要件 2
第一部 軍事制度と国家―理論的および歴史的考察
第一章 プロフェッションとしての将校職 7
一.プロフェッショナリズムと軍 7
二.プロフェッションの概念 8
三.ミリタリー・プロフェッション 10
第二章 西洋社会におけるミリタリー・プロフェッションの出現 18
一.新しい社会形態 18
二.傭兵の将校職と貴族の将校職 19
三.十八世紀の貴族的な制度 20
四.前プロフェッショナル的理想―軍事技能と生れながらの天才 26
五.プロフェッショナリズムの起源 29
六.プロフェッショナルな機関の出現、一八〇〇年~一八七五年 37
七.ヨーロッパのプロフェッショナリズム―アプトン将軍の要旨、一八七五年 51
八.プロフェッショナルな倫理の定式化―クラウゼヴィッツの『戦争論』における戦争の自律性と従属性 52
第三章 軍の精神―プロフェッショナルな軍の倫理の保守的現実主義 56
一.軍の精神の意味 56
二.プロフェッショナルな軍の倫理 59
第四章 権力、プロフェッショナリズム、およびイデオロギー―理論としてのシビル・ミリタリー・リレーションズ 76
一.シビリアン・コントロールの諸形態 76
二.シビル・ミリタリー・リレーションズの二つのレベル 81
三.不偏的シビリアン・コントロールの均衡 89
四.シビル・ミリタリー・リレーションズの型 91
第五章 ドイツと日本―シビル・ミリタリー・リレーションズの実際 93
一.ドイツと日本の形態 93
二.ドイツ―プロフェッショナルな軍国主義の悲劇 94
三.日本―一貫した政治的軍国主義 117
第二部 アメリカにおける軍の権力―歴史的経験 一七八九年~一九四〇年
第六章 イデオロギーの不変性―自由主義社会対ミリタリー・プロフェッショナリズム 133
一.アメリカのシビル・ミリタリー・リレーションズの歴史的不変性 133
二.アメリカにおける自由主義の優位性 133
三.軍事問題に対する自由主義的アプローチ 138
四.自由主義政治における軍の英雄 147
第七章 憲法体系の不変性―保守的憲法対シビリアン・コントロール 153
一.憲法における不偏的シビリアン・コントロールの欠如 153
二.憲法起草者とシビリアン・コントロール 154
三.民兵条項と軍事連邦主義―帝国の中の帝国 158
四.権力の分立―軍に対する二元的統制 166
五.最高司令官条項―政治‐軍の階層構造 172
六.シビリアン・コントロールと立憲政治 177
第八章 南北戦争前のアメリカ軍の伝統のルーツ 181
一.アメリカのミリタリズムの三要素 181
二.連邦主義の衰退―挫折したハミルトンのプロフェッショナリズム 181
三.技術至上主義 183
四.大衆主義 190
五.プロフェッショナリズム 198
第九章 アメリカのミリタリー・プロフェッションの創成 209
一.ビジネス平和主義の優位性―産業主義対ミリタリズム 209
二.孤立の歳月―暗と明 213
三.創造的な中軸―シャーマン、アプトン、ルース 217
四.プロフェッショナリズムの機関 223
五.アメリカの軍の精神の形成 239
第十章 新ハミルトン主義者の妥協の破綻、一八九〇年~一九二〇年 255
一.新ハミルトン主義の本質 255
二.マハンとウッド―軍の出版人の悲劇 258
三.失敗に帰した社会との一体化、一九一八年~一九二五年 267
第十一章 両大戦間のシビル・ミリタリー・リレーションズの不変性 274
一.ビジネス界と改革自由主義者の敵意とミリタリー・プロフェッショナリズム 274
二.改革自由主義―ミリタリズムの実用主義的利用 275
三.軍の制度 279
四.アメリカの軍の倫理、一九二〇年~一九四一年 288
第三部 アメリカのシビル・ミリタリー・リレーションズの危機 一九四〇年~一九五五年
第十二章 第二次世界大戦―権力の錬金術 299
一.全面戦争におけるシビル・ミリタリー・リレーションズ 299
二.大戦略における軍の権限と影響力 300
三.戦時権力への軍の適応 309
四.経済動員におけるシビル・ミリタリー・リレーションズ 320
五.調和と激論の成果 324
第十三章 戦後十年におけるシビル・ミリタリー・リレーションズ 328
一.シビル・ミリタリー・リレーションズの代替方式 328
二.シビル・ミリタリー・リレーションズに対する戦後の考え方 329
三.アメリカ社会における軍の影響力 336
第十四章 統合参謀本部の政治的役割 354
一.政治的役割―実質的および代弁的役割 354
二.トルーマン政権における統合参謀本部 355
三.朝鮮戦争―将軍、部隊、そして国民 366
四.アイゼンハワー政権の最初の二年間における統合参謀本部 370
五.結 論 377
第十五章 権力の分立と冷戦防衛 378
一.権力の分立のインパクト 378
二.権力の分立対任務の分立 378
三.権力の分立対ミリタリー・プロフェッショナリズム 388
四.権力の分立対戦略的一元論 393
第十六章 シビル・ミリタリー・リレーションズにおける省組織 402
一.戦後十年の組織問題 402
二.統合参謀本部―法的形式および政治的現実 405
三.監査官―国防総省の超自我 410
四.国防長官の役割 413
五.国防総省の要更改事項 420
第十七章 新たな均衡に向けて 428
一.安全保障のための要件 428
二.イデオロギー環境における変化 429
三.保守主義と安全保障 434
四.軍の理想の価値 435
注 439
訳者あとがき 482
索引 501
訳者あとがき
国家にとって軍とは何か、軍人とは何か、という問いが、近来、戦争の科学の高度化、複雑化に伴って、国家の軍事的安全保障にかかわる最も基本的な命題として、一貫して問い続けられてきた。
世界に先駆けこの問いに直面することを強いられたのは、ナポレオンに壊滅的敗北を喫したプロイセンであった。ナポレオンの天才に対抗すべく、来るべき近代戦を視野に入れた組織的陸軍の構築を目指したプロイセンは、十九世紀の半ばに至って、参謀総長モルトケが、クラウゼヴィッツの独創的な理論を一つの指標として、この命題に対する回答を、いわゆるドイツ陸軍の参謀本部理論として大成させた。第二次大戦後ハンチントンは、ドイツ陸軍の改革の歴史的過程を詳細に検証する中で、モルトケの理論の骨子に当たる価値観・概念に対し、改めてミリタリー・プロフェッショナリズムという名称を付与した。現在この価値観・考え方は、その名称と共に世界に巾広く受け入れられ、主要先進国に深く根を下ろしている。
ミリタリー・プロフェッショナリズムは、要約すれば、軍に固有の特質である「軍の精神(military mind)」―古来より論じられて来た、軍に固有の側面もしくは軍の機能上の側面を表す概念―を、プロフェッショナルな軍の倫理として定義することを特徴とする規範的価値観を表している。具体的には、社会認識におけるウェーバーの理念型もしくは理想型として軍の精神を抽象的に定義することによって、プロフェッショナルな軍人の理念像を浮き彫りにしている。ハンチントンのこの理論構築の起点となり、中核となっているのは、クラウゼヴィッツの理論の戦争の本質に関する二元性の概念である。「戦争はそれ自身の方法と目標を持つ自律的な科学であり、まさにそれと同時に、その究極的な目的が外部から与えられるという意味において従属的な科学である」という二元性である。
この二元性の概念が示していることは、言ってみれば、戦争の科学の担い手である軍人は、戦争の領域外にある政治に関与してはならない、ということである。「戦争は政治の手段であり、軍は政治家の召使いである。シビリアン・コントロールはミリタリー・プロフェッショナリズムにとって必須の要件である」ということに他ならない。ハンチントンは、このミリタリー・プロフェッショナリズムを最大化する「不偏的シビリアン・コントロール」を実現することが、国家の軍事的安全保障の最大化をもたらす必要条件としている。
この二元性の概念は、一九世紀初頭にクラウゼヴィッツが、近代陸軍の備えるべき本質的属性として予見した指針であるが、ハンチントンはこの概念が「取りも直さず正真正銘のプロフェッショナルな概念そのものを表しており、まさしくすべてのプロフェッションの本質を体現している」と直観し、これを原点に彼独自の理論構築に結実させている。ここで西欧文化が築き上げた固有の職業概念プロフェッションは、歴史的に聖職者、医者、弁護士の三業種に限定して与えられた名称であり、社会の成立そのものに必要不可欠な職業、社会が正しく機能するために必須の職業として位置付けられ、他の一般的な職業(occupation)とは峻別した特別なステータスが付与されている。ハンチントンは、軍がプロフェッションであることの正統性を、将校の高度の専門的知識・技能である暴力の管理、国家の軍事的安全保障に対する責任、そして自らの職域の専心確立と独占という代表的な三条件を挙げて改めて検証している。言うなればハンチントンは、クラウゼヴィッツの戦争の二元性の概念に導かれて、戦争の科学の領域にプロフェッショナリズムという概念を持ち込み、軍人を上記の知的プロフェッションと同格に位置付けたのである。変遷する社会的事象の本質を見通す彼の鋭敏な資質がここに如実に表れている。
我が国が、国家にとって軍とは何か、軍人とは何か、という問いに初めて直面したのは、近代国家として出発すべく、新しい国家形態と軍の創設に着手した明治維新においてである。この時期あたかもヨーロッパでは、モルトケがドイツ統一戦争を戦う中でミリタリー・プロフェッショナリズムを完成の域に高め、そのドイツのシステムを、過酷な南北戦争を戦い抜いたアメリカ陸軍が、シャーマン、アプトンを中心に真摯に学び取り、ミリタリー・プロフェッショナリズムの確立に沈潜していた時期に当たる。こうした中、鳥羽伏見の戦い、戊辰戦争などいわば前近代のサムライの戦いを制した、薩長を中心とする倒幕勢力が、暗中模索ながら、ドイツ統一戦争でのプロイセンの圧倒的進撃を追い風に、最終的にドイツの国制・軍制を範とする道を選択した。
国体と国軍の同時確立を図る難題を背負った日本は、しかし、戦争の科学の飛躍的進歩が近代国家に突き付けた不可避の難題、政治と軍事の間の距離設定が国家の存立に及ぼす第一義的な意義を認識するうえで、大きな逸機に見舞われた。木戸孝允の早逝である。岩倉使節団の全権副使として渡欧中に、残留組の西郷と山縣が、文官の地位にありながら元帥と中将の位に就いたことを激しく非難し、モルトケの例も引いて、文明国では「文武の大別判然たり」とする書状を井上馨など藩の同志に書き送っている。木戸はしかし、帰朝後四年を経ずして、国体を定める最も重要な時期に早逝した。逸機のもう一例は、木戸の推挙により陸軍に入隊し、ドイツの軍制調査のため二度にわたり渡独した、後の総理大臣桂太郎に纏わるものである。ドイツ参謀本部に日参し、モルトケから特別の知遇を得ていた桂中尉は、木戸に送った書簡に、「陸軍政令」と「文官政令」の問題に言及し、ドイツの「文武政令平均を失わず・・・相行われる源意を探偵したし」と、シビル・ミリタリー・リレーションズの問題に着眼している。木戸の死の一年後に帰国した桂は、しかし、政治と軍事の両権力を追い求める参議陸軍卿山縣中将の配下に入り、その片腕として山縣を支えて行く。軍令組織としての参謀本部設立を献策し、統帥権独立の制度的基礎を築くのに大きく貢献した。モルトケの理念「政治に関与しない陸軍」は桂の頭脳から抜け落ちたのである。
一介の武弁を標榜する山縣有朋は、中間組という下級武士から奇兵隊の軍監に取り立てられ、極めて強い政治志向の体質を押し通し、木戸をはじめ大村益次郎、高杉晋作、久坂玄瑞など長州藩の俊秀の早逝により、図らずも明治維新の実力者にのし上がっていく。軍人として元帥府に列せられると共に元老の地位を獲得し、明治・大正の政治を操った山縣が追い求めたもの、それは椿山荘の居室の暖炉の上に飾られたビスマルクとモルトケの二つの像が如実に物語っている。ハンチントンは次のように語っている、「世の中には、プロフェッショナルな能力とプロフェッショナルな服従という価値観を追求し続ける真のプロフェッショナルな人間と、それ自体を目的として権力を追求し続ける政治的な人間の二種類の異なるタイプの人間が存在する」と。「しかもこの両者の異なる本性が、大部分の人間の中にまたすべての集団の中に共存している。従ってこの両者の間の緊張状態は決して取り除くことはできない―せいぜい我慢できる程度に両者の関係を調整すること位しかできない」。
ハンチントンは、旧体制下の日本を、一貫した政治的軍国主義国と位置付け、国家的イデオロギーとしての神道と武士道を信奉する日本の将校団を「世界で最も政治的な陸軍」、「世界の主要軍事集団の中で最もプロフェッショナルな精神を欠く集団」と断定している。その特質を「日本はミリタリー・プロフェッショナリズムの外観、つまり外部を覆う殻は手に入れたが、その本質を我がものとすることができなかった」と厳しく指摘し、戦後の日本の進路について「シビル・ミリタリー・リレーションズの方式として、一九四五年以前に優勢であったものとは外見上は異なるが、本質的には異なることのない形態が日本に出現する可能性が高いように思われる」と的確に見通している。日本のプロフェッショナリゼーションの行く手には、たしかに「プロフェッショナルな軍の伝統の欠如」という過去の大きな歴史的障壁が立ちはだかっている。しかし、木戸孝允という時代を超越した一人の先達が存在していたことを忘れてはならない。先進諸国における例を見ても、ドイツのシャルンホルスト、アメリカのシャーマンに見るように、プロフェッショナル化に立ち上がった先進的改革者はごく少数に限られている。戦後三四半世紀を経た現在、我が国における国軍としての自衛隊は、創設以来受け続けた旧軍の影響から完全に脱している。木戸孝允の本質を見通す透徹した洞察力が点じた貴重な燎火を絶やすことなく、ミリタリー・プロフェッショナリズムの本質を我がものにすることが、激しく揺れ動く世界情勢に対処し、日本の軍事的安全保障を確立するうえでの核心的な前提条件となる。
六十万人を超える軍の戦死者を数えた南北戦争後のアメリカでは、大富豪カーネギーに象徴されるビジネス平和主義が隆盛を極め、「社会の全面的敵意が、軍を政治的に、知的に、社会的に、さらには物理的にも、社会から孤立した状態に追いやってしまった」。このような状況下で、アメリカのミリタリー・プロフェッショナリズムの創設を担ったシャーマン、アプトン、ルースたちは、アメリカの軍の最悪期と評されるこの孤立、排斥、縮小の時代に、「自らの権力と影響力の拡大を犠牲にして、自分自身の固い殻の中に閉じこもることで、独自の軍の個性を確立しようとした」。この間僻地に住み着き過酷な任務に携わる若年の士官、あとに続く陸軍士官学校生徒も、国民の容赦なき敵意の前に、孤立した立場に追いやられる中で、軍事学術誌などを通して、自らが担う国防の任務、意義を半世紀以上にわたって訴え続けてきた。その苦難の歴史がアメリカにもたらした果実をハンチントンは次のように表現している「十九世紀末に、もし将校団が排斥されていなかったならば、またもし陸軍と海軍が一八七〇年代と一八八〇年代に予算を骨の髄まで切り詰められていなかったならば、合衆国は一九一七年と一九四二年にもっとずっと困難な時を迎えていたであろう。二度の世界大戦において、軍の先頭に立って作戦を指揮したプロフェッショナルな将校たちの能力、その目を見張るような戦歴、それは十九世紀の終わりに彼らが排斥されたが故にもたらされたものであった。それは排斥されたにもかかわらずもたらされたものではないのである」。
日本国民は太平洋戦争で過酷な総力戦の惨禍を被り、戦争に対する強い憎悪の念が今なお心の奥深く焼き付けられている。その結果国防にかかわる問題は、戦後一貫して日本国民の関心の対象外とされ忌避されてきた。その任務に携わる関係者は多かれ少なかれ、国民的基盤から除外された立場に立たされ、社会からの孤立状態を自覚させられてきた。日本とアメリカの国家としての発展の歴史、地政学的条件は大いに異なるが、十九世紀後半にアメリカ軍人が歩んだ厳しい孤立の道、そしてその中からミリタリー・プロフェッショナリズムを築き上げた歴史は、貴重な教訓を我々に与えている。
第二次大戦終結間もない一九五一年にハーバード大学の博士課程を終え、引き続き同校の政治学部で教鞭を執るかたわら、ハンチントンは『軍人と国家』の執筆に着手した。軍事社会学の一分野に位置付けられるこの難解なテーマ「シビル・ミリタリー・リレーションズ」に取り組むにあたり、この分野に関する従来の研究を、曖昧で非体系的な仮定や信条の組み合わされた寄せ集めの理論と批判したうえで、統合化された体系的な理論的枠組みを提示するという意欲的な構想の下に本書は執筆された。
大学院で纏めた博士論文「州間通商委員会」から大きくかけ離れた、この難解なテーマを選んだ動機は何処に在ったのであろうか。本書の発刊から五〇年を経た二〇〇八年、ウェストポイントで開催された発刊五〇周年記念シンポジウムで、逝去を半年後に迎えることになったハンチントンは次のように語っている、「本書の執筆は、トルーマン大統領のマッカーサー解任に刺激を受けたことも一部影響しているが、歴史的に安定したプロフェッショナリズムと政治的中立を守り続けてきた称賛すべき将校団からインスピレーションを得たことに端を発している」。ここに賛辞を込めて彼が示した、合衆国軍とその象徴としてのウェストポイントが築き上げた伝統に対する高い評価が、『軍人と国家』執筆の動機であると共に、その中心的な命題を具現化する上での確固たるバックボーンとなっているのである。建国以来、正規軍の価値を認めない徹底した自由主義国アメリカにおいて、政治的中立を基本倫理とするミリタリー・プロフェッショナリズムを築き上げ、終始これを守り通して来たウェストポイントと合衆国軍、それは、第二次大戦中エール大学に学び、終戦直後短期間陸軍の軍務に就いたハンチントンの鋭敏な感性に、時代が必要とする本質的な価値観・倫理と普遍的な意義を感得させたのであろう。ちなみにハンチントンはその後、時代の大きな流れの変化に対応して、幅広い分野の国際政治社会問題に向き合い、独創的な視点を時代に先駆けて世に問うている。その代表例に米ソ冷戦時代終了後の一九九六年に発表した『文明の衝突』が挙げられる。ここでは冷戦後の世界の紛争の形態を、イデオロギーの対立から文明間の衝突への変貌と捉えている。
本書は発刊と同時に全米で広く議論を巻き起こした。だが、発刊五〇年にあたる二〇〇八年時点までに十五版を重ね、現在はシビル・ミリタリー・リレーションズに関するアメリカで最も影響力のある書、あるいはこの分野におけるスタンダード・タイトルとの高い評価を得て、この分野の不動の名著として読み継がれ現在に至っている。
本書の発刊後、核兵器の拡散、中南米・アフリカ等の開発途上国における軍事政権の樹立、さらには米ソ冷戦の終結等、地政学的環境の大きな変化に対応して、ハンチントンの理論に対する反論が提起されてきた。これらの反論は基本的に、安全保障にかかわる諸条件の変化に対するハンチントンの基本理論の整合性を論じたものであり、対文民の関係において軍の特質・役割の変容を論証することを基調としている。戦争の科学と地政学的環境の変化に対応して提起されるこれらの議論はもちろん、この分野の理論的深化に重要な貢献を果たしているが、同時にハンチントンの基礎理論の重要性を再認識させている。
本書は本来シビル・ミリタリー・リレーションズに関する理論の書として著された学術的著作であるが、アメリカの知性を代表する若き一知識人が、合衆国軍と合衆国軍人に対して示す深い信頼と期待、合衆国の安全保障のあるべき姿を説くひたむきな姿勢は、単なる理論の書の範疇を超えて多くのことを我々に語りかけてくる。本書を手に取られた読者諸氏は、ウェストポイントに対する信頼と期待を、アメリカ社会の現状と対比させ熱く語る、巻末の一節*にまず目を通されることをお勧めしたい。
二〇二一年一二月 原 躬千夫
*巻末の一節(第十七章 新たな均衡に向けて 四.軍の理想の価値 435)
ウェストポイントは軍の理想を最高の形で体現している。ハイランド・フォールズは、アメリカの精神を最もありふれた形で体現している。ウェストポイントは多彩な海に浮かぶ灰色の島である。さながらそれは、バビロンの真只中に置かれたスパルタを思わせる。
軍の価値観―忠誠、義務、自制、献身―が、今日アメリカで最も必要とされている、ということを否定できるであろうか? またウェストポイントの規律ある秩序が、メインストリートのけばけばしい個人主義よりも多くのことをアメリカにもたらす、ということを否定し得るであろか? 歴史的に見てこれまで、ウェストポイントの美徳はアメリカの悪徳であり、軍の悪徳はアメリカの美徳であった。だが今日アメリカは、ウェストポイントがアメリカから学ぶ以上のことを、ウェストポイントから学ぶことができる。
軍人は秩序の擁護者であり、重い責任が課せられている。彼らのなし得る最大の貢献は、常に自己に忠実であること、そして軍のしきたりに従って勇気を持ち、沈黙を守って、粛々と軍務に邁進することである。彼らが軍の精神を放棄するならば、最初に自らを滅ぼし、そして最終的には国家を破滅させることになる。文民が軍人に軍の基準を固守することを可能とするならば、最終的には国家自身がその基準を自己のものと成して、救いと安全を見出すであろう。